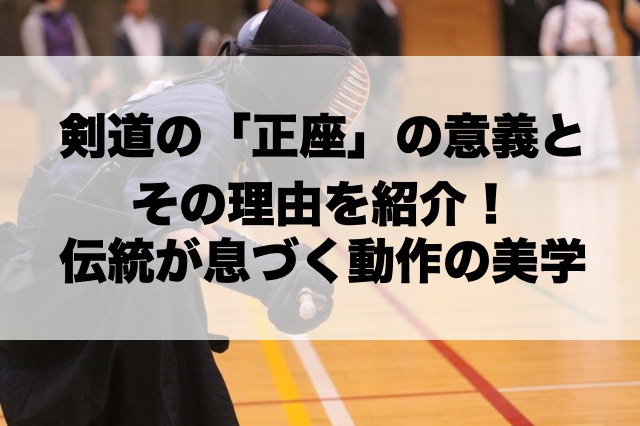
普段、正座をする機会が少なくなった現代、特別な場でのみ行われることが多い正座。しかし、剣道の世界では、正座が技術と精神を支える重要な所作です。剣道では、正座と立ち上がりに「左座右起(さざうき)」という独特の手順が定められていますが、これにはどのような意味があるのでしょうか?この記事では、その意義と背景について探ります。
座り方の作法って?
座り方の手順
- 立った状態から左足を一歩後ろに引き、そのままの姿勢で左の膝は床につきます。このとき、左足のつま先は立てておきます。
- 右足も左足と同じように膝をついて、両足の膝をついた中座の状態になります。両脚ともつま先は立てたままです。
- 両足のかかとにお尻がつくように腰を下ろします。この姿勢を「跪座(きざ)」といいます。
- 跪座から正座にしていきます。少し腰を浮かせ、右のつま先を伸ばして座ります。このとき、前屈みにならないように注意します。右足の親指の上に左足の親指を重ねます。
- 最後に、お尻を踵の上に乗せて正座の姿勢となります。
立ち方の手順
正座の姿勢から跪座に変えていきます。
- 両足の太ももに少し力を入れ、お尻を軽く浮かせます。左足からつま先を立てて、跪座の状態になります。このとき、上半身が前屈みにならないよう注意します。
- 跪座から少し腰を浮かせ、正座とは逆の順番、右足を先に立てます。左足の膝と右足のつま先が揃うようにすると奇麗です。
- 左足を立てて、前屈みにならないよう立ち上がります。
- 右足を左足に揃え、立座となります。
手順1、2の中座になる行動は、長時間の正座から立座になるときに、ふらつくことのないよう足に血の巡りを良くするための重要な動作となります。足の指を反らせ、筋を伸ばすことで血液を循環させ、足の動きを良くします。したがって、ふらつきそうなときは、この姿勢を少し保ってから動くとよいでしょう。
「左座右起」とは?剣道における基本動作の一つ
正座の所作は単なる礼儀作法を超え、武士の心構えや戦術の要素が込められています。「左座右起」とは、剣道において正座する際には左足から座り、立ち上がる際には右足から起き上がる動作を意味します。この所作が生まれた理由には、武士が刀を腰に差して歩いていたことに関係しています。
立ち上がるときに右足から起きる理由は、右手で刀を瞬時に抜けるようにするためです。逆に左足から立ち上がろうとすると、左ひざが刀の抜刀の邪魔になってしまうため、戦闘時には不利になる可能性があるのです。このような動作の順序は、戦いに備えた所作として実践され、現代の剣道でも受け継がれています。
武士の所作が示す信頼と気配り
「左座右起」は、武士の精神とともに相手への配慮や警戒心の表れでもあります。
敵に対する警戒心を示し、臨戦態勢を取る際は左側に刀を置くことで瞬時に抜刀できる体勢を整えます。反対に、相手に信頼を示すためには「右座左起(うざさき)」のように、右側に刀を置き立ち上がりも左からとする方法もあります。これにより、相手に対して戦意がないことを表現することができ、刀を抜くのに時間がかかることで信頼を示すことができるのです。
現代では実戦の場はありませんが、このような気配りと信頼の所作は、相手に対する思いやりや礼儀の心として生かせます。剣道を通じてこうした精神を学ぶことは、日常の対人関係でも応用できるでしょう。
日常生活で役立つ「左座右起」の所作
剣道の正座で使われる「左座右起」は、集中力を高める方法としても活用できます。日頃から所作が綺麗な人は周りから「きちんとしている」という印象を受けます。周りの印象も良好になりますし、集中して話を聞きたい時や、重要な場での所作として、この座り方を試してみてはいかがでしょうか。

